
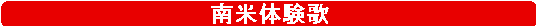
| 南米体験歌トップ | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 第4部 | 第5部 |
 第2部 ブルサコ仲屋農園で 初めての花作り
第2部 ブルサコ仲屋農園で 初めての花作り
-目次-・ 13. アルゼンチン第1日目、仲屋さん家族からの歓迎
・ 14. 目指すは独立! いよいよ花作りスタート
・ 15. ガルポン完成、仲屋農園での生活
・ 16. 花卉実習青年の独立とパトロン側の事情
・ 17. パトロンへの募る不信感、仲屋農園から飛び出す
・ 18. 高山さんとの出会い、エスコバルへの道
13.アルゼンチン第1日目、仲屋さん家族からの歓迎
ブエノスアイレスの町を過ぎると、あとは石畳が延々と続いていく。右も左も全くの牧草地だ。これが、有名なパンパスだ。ふっくらした牛がのんびりと草をはんでいる。
「川島君、すごいでしょう?アルゼンチンの人口は2,300万人だけど、牛の数は5,000万頭です。
すなわち、国民一人に2頭の牛ということになります。これから行く私達の農場で、皆がアサードをして待っているよ」。
パトロンの農場はブルサコ市にあって、ブエノスアイレスからはわずか30キロメートルの位置にある。
しかし、いったん町を出ると、このようにもう全く何もない。あるのは、牧草地と牛の群れだ。
この間に仲屋さん兄弟がスペイン語で話し合っていた。その中で、時々ブルサコとか、ブエノスアイレスとか、何々カージェ、何々アベニーダ、そして人の名前のような固有名詞が飛び出た。私は、この二人のやり取りを聞いて、「なんてすごいんだ。いつになったら、この二人のようにスペイン語が流暢に話せるようになるのだろう」と感激した。
それから間もなくして、昔ジョンウェインの西部劇で見た開拓地の門のようなところに到着した。そこには、簡単な針金が捲きつけてあった。兄の善行さんが車から降りて、それを外し、車を中に入れてから再び捲きつけた。「川島君、ここが私の農園だ。今日から君はここの住人だ」。そこは見渡す限りの草原。奥の方に、何棟か温室のようなものがある。「川島君、ここは全部で50町歩あるんだ。広いだろう?」。
私達はさらに奥へ進んだ。すると、何人もの人たちが私達を待っていた。プーンといい匂いがしてきた。彼等はアサードをしていた。アサードとは、焼肉のことだ。買ったばっかりの何キロもの肉をステーキ用の大きさに切って、炭火でじわじわ焼いていく。ソースは全くかけない。調味料は唯一、塩だけ。「川島君、ようこそアルゼンチンへ!こちらが私の家族です。そして、こちらの青年が今一緒に働いてくれています。また、こちらの家族は、最近パラグアイからやって来た清水さん一家です。腹いっぱいアルゼンチンのアサードを食べてください」。私は今まで、これほどの量の肉を見たことがなかった。手をちょっと伸ばせば、いくらでも食べられる。そして、その肉のおいしいこと、また新鮮なこと。
こうして、げっぷが出るほど肉をたくさん食べた。「川島君、実を言うと、君の部屋はまだできてないんだ。君が着くのが予定よりずっと早くて、君のガルポン(小屋)を作るのが遅れてしまったんだ。だから、すまないが2〜3日、息子の部屋に寝てください」。
夕食は仲屋さんの家族と一緒に食べた。仲屋さん一家は、奥さんのよしえさん、そして長女スサナ、次女エリカ、長男カルロスの5人。その他に私と同じ日本からの農業実習生が二人、さらにパラグアイからやって来た清水さんの家族5人。清水さんの家族は農園の中央にガルポンを作ってもらい、そこに住んでいた。まだ、子供さんたちは小さく、大変な様子だった。こうして、私のアルゼンチン到着第1日が終わり、明日からは農園の作業が始まる。
ブエノスの 熱き大地に わが命
アサードを いくら食べても なくならず
税関を 通るためには これチップ
上に戻る14.目指すは独立! いよいよ花作りスタート
まだ暗いうちに目を覚まして、水道の蛇口をひねり、顔を洗った。乾いた手ぬぐいで顔を拭き、そのまま温室のほうに向った。なんと、そこにはもう既に奥さんが来ていて、仕事をしていた。「おはようございます。私は何をしたらいいですか?」「川島君、おはよう。それではこのマセータ(鉢物)の手入れを教えるから、こっちに来てちょうだい」。
この温室には、出荷間近の何千個もの鉢物があった。これを一つづつ手に取り、小さな草をとったり、きれいにして商品にするのが仕事だった。この温室は全てこれらの鉢物であったが、他の十棟にもおよぶ温室には、それぞれバラを植えてあったり、カーネーションが入っていたりしていた。これらの温室の作業をするのが私達の仕事だった。奥さんのやり方を見習いながら、私は一個一個丁寧に仕上げていった。こうして、私のアルゼンチンでの花作りが始まった。
「川島君、昼飯だよ。こっちに来なさい」。そこは母屋の食堂で、既にパトロンの仲屋さんを初め、他の青年達も来ていた。これらの食事は、まだ若い私とあまり年が違わない二人のお嬢さんが作ってくれていた。大きな皿の中には、フライパンに油を薄くひいて焼き上げた大きなビーフと、白いごはんが大盛りに添えられていた。このご飯はすべてアルゼンチンで獲れたお米だった。それに豆腐の味噌汁が加わった。私が日本で食していたあんぱんと牛乳だけの昼食とは、大違いだった。
こうして、毎日朝早くから一生懸命仕事をし、日本では味わった事のないたくさんの肉料理を食べながら、私の移民生活は続いた。
これほどの 牛肉を食う アルゼンチン
目を覚ます 顔を洗って 温室へ
川島君 こうして作る 鉢物は
上に戻る15. ガルポン完成、仲屋農園での生活
休日は日曜日だけだった。私とたいして年の違わない仲屋さんの長女スサナは、このブルサコの日本人会が主催する運動会のスターで、ここ2年間、百メートル走と2百メートル走少女の部で優勝し、今年も優勝は間違いないだろうと言われていた。しかし、日本語はまったく話せず、会話をしたいと思っても、私のスペイン語もたいしたことはなかったので、おまけにパトロンのお嬢さんということもあり、どうしても気後れして話すチャンスはなかった。
こうして、1週間が過ぎ、ある日、私は奥さんに「あの先輩の人たちは、何をしているのですか?」と聞いた。すると、「川島君、彼らは遊んでばかりいて悪い人たちだから、近づいてはだめよ」。この言葉に私は愕然とした。どうしてそんなことを言うのか分からなかったが、パトロンの奥さんがはっきり言ったことだし、彼らに近づくのはやめようと思った。
この他に仲屋農園には、パラグアイから渡って来た山下さん一家がいた。彼らは6年前、夫婦でパラグアイに移住したのだが、いくら働いても食べるだけが精一杯で、日本で考えていた生活を実現するのはとても不可能だと考え、ここアルゼンチンにつてを頼って渡ってきたのだった。この50町歩の仲屋農園の全ての温室を作ったり、修理したり、手入れをするのが彼の主な仕事である。この農園のど真ん中に小さなバラック小屋を建て、そこに夫婦と幼い子供3人と住んでいた。奥さんは、さすがに山下さんの悪口は言わなかったので、日曜日の休日には山下さんの家に行って、色々話をした。
このような具合で、私の移民生活は始まった。最初の1週間はパトロンの長男ホルヘの部屋の中に簡単なベッドを置いてもらい生活していたが、次の日曜日に山下さんが中心になって母屋のすぐ脇に簡単なガルポン(小屋)を作り、その中に私のベッドを移した。床はまったくの土で、シャベルできれいにならしただけだった。したがって、ベッドから下りてそのまま床に足を触れるとひんやりし、その冷たさは頭の芯まで上ってきた。しかし、鍵のついたまあまあのドアも付けてもらい、こうして自分一人、他人に気遣うこともなく、日々の生活ができるようになった。
しかし、仲屋農園から外へ行くということは、とてつもない大変な作業だった。とにかく周りには何もなく、このような農園がたくさん続いているだけなので、全く外へ遊びに行くということはできなかった。ただただ、奥さんから言われるままに一生懸命働いて農園に尽くすことが、私の使命だった。こうして作業を覚え、生活にも慣れて、山下さんの家に遊びに行ったのだが、その時つい、「この間奥さんから、あの二人の青年はとても悪い人たちだから、近づいてはだめよと言われたけれど、どうしてですか?」と聞いたところ、「そんなことを言ったのか。川島君、私は6年間パラグアイで一生懸命頑張ったが、ここ仲屋農園の生活のほうがずっと厳しい。こうしてただ、働くだけだ。おそらく、彼らももう2年以上働いて独立の時期が来たので、追い出そうと思っているのだろう」という答えが返ってきた。
ガルポンを ついに作った 半日で
何もない 周りを見れば 土地ばかり
上に戻る16. 花卉実習青年の独立とパトロン側の事情
私はまったく気がつかなかったのだが、私達花卉実習青年は、いちおう2年間の労働契約で働き、その後はパトロンが資金面などを援助してくれて、独立の方向へ持って行ってくれるという事になっていた。正式な契約書は交わしていないが、お互いの口約束みたいなものがあった。
しかし、昔と違って今は花卉業者があまりにも増え、その反面、花の需要は頭打ちで、逆に減少傾向にあり、このままでは皆、共倒れしてしまうという危機感があった。仲屋農園に働いている二人の青年も既に2年間の就労を終え、これから独立するつもりで頑張ってはいたが、仲屋さんにとっては二人を独立させるためには大変な金額を使うことになり、さらに将来の商売敵にもなるわけで、非常に難しい選択を強いられていたわけである。
しかし、私達青年にとっては、こうして朝から晩まで一生懸命仕事をして頑張っているのは、将来独立できる希望があるからで、そのために毎日8時間以上働き、残業手当を一銭も貰わないのもまさに独立の時の援助を期待しているからだった。もし日本人のパトロンが現地の人を雇用する場合は、アルゼンチンの労働法によって色々な制限が課せらる。彼らに法律どおりの残業代、手当て、諸々の経費を支払ったら、それは大変な金額になり、とても人を使うことはできない。しかも、多くのパトロンはスペイン語を十分に話すことができず、その面でも多くの問題が生じていた。
こうした環境の中で、パトロン達は亜国拓殖組合(亜拓)を設立し、ブエノスアイレス市の中心街にある日本の移住事業団と連携して、花卉実習青年を呼び寄せているのだった。このような青年であれば、働く意欲もあるし、言葉も通じるし、朝から晩まで自由に使えるし、非常に便利だからである。
2年間 がんばれよ君 独立へ
働けど 働けど今 悪くなる
上に戻る17. パトロンへの募る不信感、仲屋農園から飛び出す
私は山下さんの話が非常に気になったので、その晩青年達のガルポンに行った。「川島君、今までどうしてこなかったのだ。」「奥さんから貴方たちに近づくなと言われたので、それで」「俺たちの事を何て言っていたんだ。」「遊んでばかりで悪い人たちだと言っていました」。「全く残念だ、俺たちは今まで一生懸命頑張ってきたのに、おそらくこれから俺たちを独立させなければならないので、新しい青年も来た事だし、もう用がないんだ。」それからいろいろな事を話した。話してみると、彼らは全く普通の真面目な青年達だった。もっともっと聞きたかったが、夜もふけて明日の仕事に差し支えるので、自分のガルポンに戻った。あまりにも色々な事がありすぎて、その晩は中々眠れなかった。
それから2、3日たって仲屋さんが私達を母屋の居間に呼んだ。「最近の君達の様子がおかしい。一体どうしたのだ。川島君、君は来たばかりだからここに居なくていい、出て行ってくれないか?」このパトロンの言葉を聞いて私が「仲屋さん、貴方は悪い人だ。彼らを独立させたくないので、こうして追い出そうとしているのだ。こんなことなら、私がここを出て行きます。」と言うと仲屋さんは驚いた。まさか着いたばかりの青年からこのような言葉がでてくるとは思わなかったのだろう。「川島君、君は出て行く必要はない。まだ着いたばかりではないか。」「仲屋さん、私の気持ちはもう決まりました。早速明日亜拓に行って事情を話してきます。」ここまできたら止まるわけにはいかない。青年達もこの私の突然の言葉にビックリして、ただ唖然として聞いていた。
次の日、駅の方角を聞いて私はそちらの方へ向った。とにかくかなりの距離を歩いた。そして駅に着くと「ブエノスアイレスまで幾らですか?」という私のたどたどしい言葉を聞いて駅員は「トレシエントス・ペソス」と答えた。アルゼンチンペソは日本円に比べて約一割ほど高かったので、そうか330円ぐらいか、それにしても高すぎるな、と感じたが、私にはまだこれに反論するだけの力がなかった。こうして私は約三ヶ月ぶりにブエノスアイレスの街に着いた。そしてタクシーに乗って亜拓へ向った。
港で出迎えてくれた背の高いあの須古さんが会ってくれた。「川島君、さっき仲屋さんから電話で事情を聞いたよ。君はまだ着いたばかりだし、こんな事では誰も雇ってくれないよ。早く仲屋さんのもとに帰りなさい。良くお詫びをしてもう一度働かせていただくんだ。」考えて見れば仲屋さん達パトロンが作った組合だ、彼らの支払う会費によって運営されているわけだ。私達の話が届くわけはない。事情を把握した私は駅へ戻り、今度は用心して駅員に値段を尋ねた。「クワント エス ア ブルサコ?」「トレインタ・ペソス」何と来た道の十分の一ではないか。くわばら、くわばら、これからはもっと注意しよう。
注意せよ 周りはみんな 敵ばかり
外人に 優しくするは 日本だけ
上に戻る18. 高山さんとの出会い、エスコバルへの道
無事に仲屋農場に戻る事ができた。亜拓の須古さんには、「もう一度謝って、働かせてもらうように」と言われてはいたが、私は2度と戻るまいという気持ちが強かった。それで日が暮れるのを待ち、大工の山下さんのガルポンに行った。「山下さん、どなたか紹介してもらえないでしょうか。ここにはもういられません」。「そうか。そうだ、あの日本食を作っている高山さんだったら誰か知っているだろう。彼の家は近くだから、これから行ってみよう」。こうして、私達はその高山さんの家へ向った。
高山さんの家族は、山下さんと同じように最初はパラグアイに移民したのだが、そこでは作っても作っても市場がないため、お金が入らないので、結局は食べるだけの厳しい生活になってしまった。そのような境遇に逆らって、ついに家族中でここブエノスに引っ越してきたのだった。そして、昔勉強した日本食の知識をもとに、小さな工場を始めたのである。
始めてみると、日本食に欠かせない、みそ・しょうゆ・納豆などが意外と簡単にできて、しかもそれが日本人移住地で飛ぶように売れた。今では、3台の軽トラックと2台の自家用車を持つまでになっていた。近くの家といっても30分ばかり歩いただろう、バラック造りの大きな平屋が見えてきた。「あれが高山さんの家だよ」。とうとう高山さんの工場兼自宅に到着した。
「こんばんは。高山さんいませんか?山下です」。「おお、山下君か。良く来たな。今日は何の用事だ?」。中からほっそりした紳士が出てきた。頬がとがって、しかし眼光は鋭く、じっと山下さんや私のほうを見つめていた。すると山下さんは、「こちらは川島君です。3ヶ月前に日本から来たのですが、仲屋さんとうまくいかなくて、どこか他に行きたいと言っていますが、どなたかお知り合いはいないでしょうか?」と聞いてくれた。
私は高山さんに今までのいきさつを話した。私達が訪ねた時、高山さんはちょうど自分の息子さん達にマーケティングの講義をしていたところだった。高山さんはパラグアイとブラジルにそれぞれ奥さんがいて、このブエノスの夫人を入れると合計3人、子供さんも12人いるが、このうち5人は養子だそうだ。このブエノスには、半分の6人の子供さんがいて、就業後毎日、こうして黒板の前で色々な講義をするのが日課になっていた。
「そうだ、明日息子の孝がエスコバルへ行く。彼と一緒に行ったらいい。あそこには、たしか杉田さんが日本人の若いムチャーチョ(青年)を欲しがっていた」。こうして話は決まった。明日は、ここブルサコから70キロメートル離れた花の町エスコバルへ行く。
ブルサコを 離れて次は エスコバル
エスコバル 花の都と 歌いけり
ぶつかって 当たって砕けろ 人の道
上に戻る








